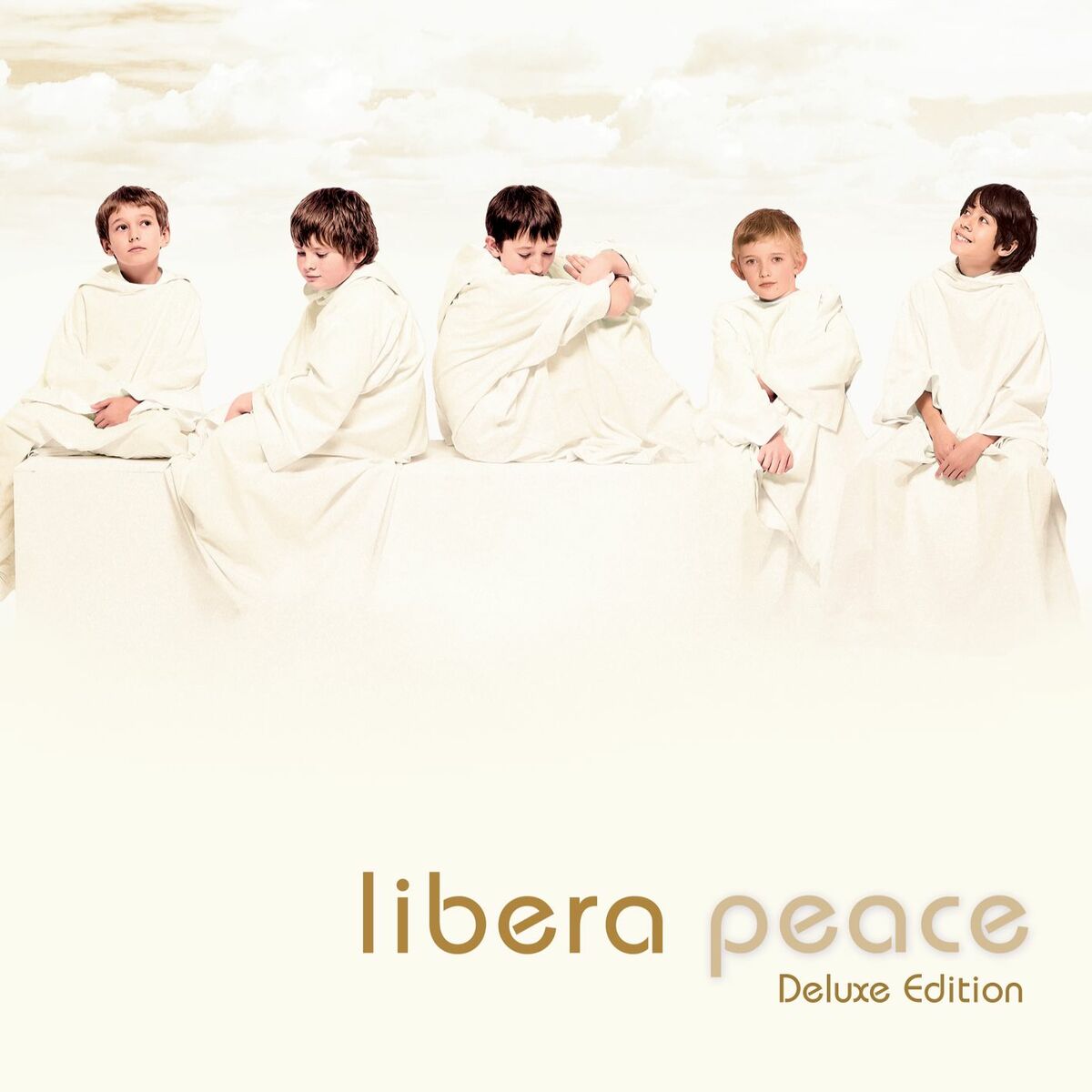
待降節(Advent)第一主日は、 クリスマスの準備をはじめる日。
教会ではこの11月30日の「聖アンデレの日」に一番近い日曜日から、一週間に一本ずつ、蝋燭に火をともしていく。
1週目はやさしい心を持つことができるように。 2週目は丈夫な心を持つことができるように。 3週目は忍耐強い心を持つことができるように。 4週目はお祈りする心ができるように。祈りながら、火をともす。
そんなアドベントの季節に、クリスマスの音楽の歴史もひもとく、というのが今回のテーマだ。
教会から生まれたクラシック音楽には、もともとクリスマスと縁の深いものが多い。バッハの教会音楽はもちろん、フェリックス・メンデルスゾーンのカンタータは讃美歌98番「あめにはさかえ(Hark! The Herald Angels Sing)」として日本でも広く知られているし、チャイコフスキーの「くるみ割り人形」は欧米の人にとっての年末の風物詩といえるだろう。
今回は、そんなクラシックの中でも「キャロル」と呼ばれる古い伝承歌に注目してみた。静謐な合唱のあわいからしみいる、クリスマスの本質に迫ってみよう。
1) キャロル・オブ・ザ・ベル(12/10放送分)
ウクライナの古い民謡を元に、司祭マイコラ・レオントーヴィッチュが1914年に編曲した名曲である。
1936年には、やはりウクライナ出身の作曲家ピーター・J・ウィルウフスキーによって英語の歌詞が付けられ、作曲から100年以上経った今日において、最もよく歌われるクリスマス・キャロルの一つとなった。多くのアーティストによってカバーされ、『ホーム・アローン』をはじめとする多くの映画やテレビ番組などで使用されてきたから、ご存知の方も多いはずだ。
楽曲は、4分音符を基調とするオスティナートによって構成されている。メロディはウクライナの新年の歌「シェドリック」がモチーフだ。
ベルの音を聞こう ベルの音が心地よく語りかける 不安はきっと消え去ると
神秘的な響きで歌われる歌詞が、平和を願う世界中の人々に再び注目されている。ここ数年、いまを生きる作家家によって新たなアレンジも生まれているので、ぜひ注目してみてほしい。
2) コヴェントリー・キャロル(12/11放送分)
英国伝統のクリスマス・キャロルにして、私のお気に入りのスティングの1曲。キャロルの作者は不明だが、16世紀にはイギリスのコヴェントリーで劇中歌として歌われていたものだという。
題材は新約聖書だ。生まれたばかりの救世主を恐れたヘロデ王の「幼児虐殺」から、神のお告げでイエスたちは逃げ延びる。もしかしたらそのとき、聖母マリアはこんなふうに歌っていたのかもしれない、と思わせる愛に満ちた曲だ。
演奏するスティングは、1951年イングランド生まれ。1977年にロックバンド「ポリス」を結成し、バンド解散後もシンガーソングライターとして第一線で活動を続ける彼は、2009年にクラシックの名門ドイツ・グラモフォンからもアルバムを発表している。題して『ウィンターズ・ナイト』。英国の伝承歌からシューベルト、そしてバッハの器楽曲に自作の詞をつけたオリジナル曲まで多彩で、かつ統一感のあるすばらしいアルバムだ。
スティングによると、舞踊のための民謡だったキャロルがクリスマスと関連付けられたのは13世紀頃。19世紀にいたるまでのキャロルは教会に強く結びついていて、神秘的で静謐なものが多いそうだ。ロックなスティングは商業的クリスマスについては懐疑的なのだが、さまざまな時代の作曲家たちのインスピレーションを掻き立てるキャロルの伝統には、深い敬意を払っている。
この曲もたしかに、複雑な美しさと内省的な雰囲気を持っている。Lully, lully, (ねんねねんね、おやすみよ)と、祈りのように繰り返されるリリックと、ラストの希望に満ちたハーモニーは、何度聴いても心に沁みる。
3)オー・ホーリー・ナイト (12/12放送分)
バレエ『ジゼル』などで知られるフランスの作曲家、アドルフ・アダンが作曲したキャロルである。
原題は「クリスマスの賛美歌(Cantique de Noël)」。原詩はプラシド・カポーによるものだが、ジョン・サリバン・ドワイトがかなり自由に英訳した「O Holy Night, the stars are brightly shining」で世界的に有名になった。
アダンが活躍した19世紀は、現代につづくクリスマスのイメージが生まれた時代だ。
大きなクリスマスツリーと、その周りに置かれたたくさんのプレゼント、テーブルの上のお菓子やご馳走。こうしたクリスマスの情景は、ヴィクトリア朝時代に完成したものだとされている。
よく言われる伝説が「ヴィクトリア女王によるクリスマスツリー導入説」である。ドイツ生まれのアルバート王子と結婚した彼女が、夫が幼少期を過ごしたドイツの伝統を取り入れ、国民の模範となるべき「理想の家族のイメージづくり」に取り入れたというもの。事実は少し異なるようだが、この時代にクリスマスの行事が「家族愛」と結びつき、しだいに国民にも広まっていったというのはありうる話だ。
そしてこの時代、産業革命によって中流以上の家にはピアノがおかれるようになっていた。クリスマスの日には家族でピアノのまわりに集まり、キャロルを歌う───こうした光景も19世紀に生まれたものだろう。この曲も、おそらくそうした流行の中でスタンダードナンバーになっていったのではないだろうか。
この傾向は、20世紀のアメリカで無邪気に、商業的に強化されていった。大切な人と過ごすクリスマス、そんな標語を嫌う人もいる。しかし私はキャロルを聴くたびに、やっぱりクリスマスが好きだと思う。キャロルは、互いを想いあうために生まれた音楽だからだ。
クリスマスを待つアドベントは、周囲に感謝を伝える季節だと思う。誰かとパーティーをするのではなく、誰かのために一人静かにクリスマスカードを書いたり、祈ったりしながら、自分自身の心を見つめる季節。
心をこめて選んだ音楽で、そんなクリスマスの本質を思い出していただければ幸いだ。
クラシック・プレイリスト、次回の担当分は1月14日より放送予定。テーマは「ベルサイユのばら」です。毎朝5時台、JFN系列38の全国FM局とradikoタイムフリーでもお聴きいただけます。(※放送は終了しました。)
