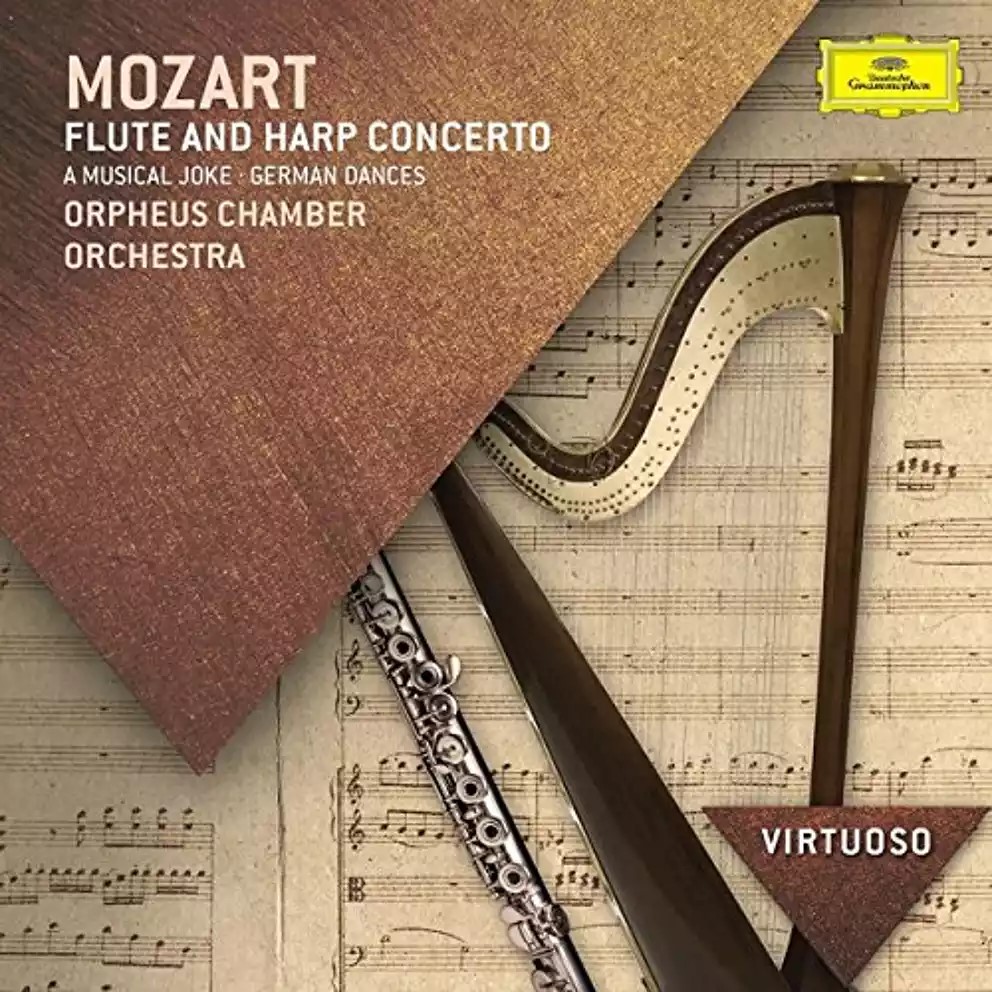
劇場やコンサートホールで、ふいに響き渡ったハープの調べにはっとしたことがある。
私たちを一瞬で異世界に運び、天上の音楽を聴くような心持ちにさせてくれる音色。そして、美しい曲線を描く楽器のかたち。ハープは、数ある楽器のなかでも特別にエレガントな存在だ。
2024年の夏、日本を代表するハーピストとして世界中で活躍を続ける吉野直子さんにお話を伺う機会があった。巨匠たちとの思い出や、じつは肉体派な演奏旅行の舞台裏。なによりも音楽への献身に胸打たれる、宝物のような1時間だった。
あんなにも目立つ存在なのに、ハープの特集は音楽雑誌でもなかなかお目にかからない。イメージとしては身近でも、あの巨大な楽器を奏者自らが運ぶことすら知らなかった。
知っているようで、じつは謎だらけのハープの世界。今月は楽器の基礎や歴史、今をときめくハープ奏者のスターなどをご紹介しながら、47本の弦が織りなすハープの奥深い魅力を探ってみよう。
1) フォーレ:即興曲 作品86(10/15放送分)
私たちがイメージするハープは、「ダブル・アクション・ペダル・ハープ」という大型の楽器だ。
柱、腕木、ボディという3つの木製パーツが三角形に配置され、奏者はボディを抱きかかえるような体勢で、指で弦をはじいて演奏する。腕木から伸びる弦は47本。音程順に並んでおり、識別しやすくするためにC弦とF弦は色付きだ。柱の下の台座には7つのペダルがあり、弦の音程を変えるためせわしなく活躍する。
ハープは、自分と楽器との間に鍵盤などが介在せず、直接体に響く点が魅力です。一方で、出した音をコントロールすることが難しい楽器でもあります。音は伸ばせないし、止めようとしても完全には消せない。ここ何年かは、余計な響きをどう消すかを重視するようになりました。そこに正解はないし、会場や環境によっても変化する。難しさでもあり、やりがいでもあります。
またハープは、色彩感を大切にするフランス音楽と相性がよくて、オーケストラ作品ではドビュッシーやラヴェル、ベルリオーズなどがとても効果的にハープを使っています。ソロでは、リストの「愛の夢」などを編曲したハープ奏者、アンリエット・ルニエの作品がとても好きです。
吉野さんが教えてくれたとおり、フランスにはハープの名曲が多い。
1904年、ガブリエル・フォーレが作曲したこの即興曲は、パリ音楽院のハープ科教授だったアルフォンス・アッセルマンのクラスの課題曲だった。手書きの楽譜の断片にはアッセルマンの筆跡も残っていて、技巧的な部分はふたりの共作だったのではないかともいわれている。
名ハーピストが手がけているからこそ、この曲には華麗なテクニック、豊かなハーモニクスといったハープの魅力がつまっている。世界中のハープ奏者たちの基本の1曲であり、1931年にアルフレッド・コルトーがこれをピアノで披露したため、ピアノ曲としても有名になった。演奏はもちろん、吉野直子さんだ。
2) モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲 第1楽章(10/16放送分)
ハープの起源は古代からある。初期のハープは狩猟に使う弓矢の弓から生まれたといわれ、例えばエジプトの王家の谷にある壁画にも、紀元前1400年頃の弓型ハープが描かれている。ハープの一種リラを奏でるギリシャ神話の吟遊詩人オルフェウスもまた、愛妻を失った男性だった。
しかし18世紀、ハープを愛したのは女性たちだった。フランス王妃マリー・アントワネットもまたハープを愛し、自作曲で来客を喜ばせ、幽閉中にはその音色を慰めにした。美しい手や巧みな指さばきを披露できるハープはもともと令嬢たちの嗜みだったが、アントワネットの登場によって人気は過熱。1780年代には令嬢の必修科目になった。
この協奏曲は、当時フランス音楽修行中だったモーツァルトが、ド・ギース侯爵の令嬢の結婚式のためにと依頼され、フランス宮廷様式をふんだんに取り入れ作曲したものだ。令嬢は、モーツァルトが作曲を教えるほど音楽好きだったらしい。フルートを愛する父侯と、ハープを愛する令嬢の晴れの舞台のための曲であり、ハープの花形コンチェルトとして残ったのも納得の華やかさだ。
3つの楽章からなるこの曲は、第2楽章のアンダンティーノがとくに有名だが、今回は溌溂とした第1楽章をご紹介しよう。
演奏はグザヴィエ・ドゥ・メストレ。男性中心の20世紀クラシック音楽の世界で、作曲家・教師としても活躍したアンリエット・ルニエらの活躍もあって、今や女性奏者のイメージが強いハープの世界。しかし、元ウィーン・フィルのハープ奏者として鮮烈にデビューした彼を筆頭に、近年再び男性のスターも増加中している。
重さ約40キロの大型楽器の、太く張力の強い47本の弦の音。その力強さに注目すると、ハープの新しい世界が見えてくるはずだ。
3) ヴォーン・ウィリアムズ:グリーンスリーブスによる幻想曲(10/17放送分)
オーケストラのなかで、ハープが鮮烈な印象を残す名曲も数多く作られている。
とりわけ有名なのがチャイコフスキーのバレエ音楽。『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』のなかで、ハープの音色とともに現れる美しい舞台にときめいた方は多いだろう。ベルリオーズの幻想交響曲の第2楽章「舞踏会」なども同様だ。スメタナの組曲『わが祖国』では、第1曲「高い城」の冒頭で、吟遊詩人による王国の栄枯盛衰の歌を2台のハープが奏でる。
ヴォーン・ウィリアムズの幻想曲もまた、冒頭のフルートとハープが私たちを中世の世界へ連れて行ってくれる。
エリザベス1世の時代のヒットソング「グリーンスリーブス(緑の小袖)」を基にしたこの曲はもともと、シェイクスピア『ウィンザーの陽気な女房たち』原作のオペラ『恋するサー・ジョン』の間奏曲だった。ハープの幽玄の響きは歴史もの、ひいては歴史をもとにした異世界ファンタジーと相性がいい。
吉野さんのような名手も、オーケストラの一員として参加するときにはその世界観を堪能し、新しい発見をすることがあるそうだ。その豊潤な経験について伺ってから、私の中のハープの概念も大きく変わり、オーケストラの中から浮かび上がる音に耳をそばだて、その音が暗示する物語に思いを馳せるようになった。
(大切なことは)音楽に誠実であることです。作曲家が遺してくれた素晴らしい音楽を、私のハープを通して聴衆に伝えること、それが役割だと思っています。ハープは楽器の形や音の響きから優雅な楽器だと言われますが、決してそれだけではありません。エレガントなだけではない、自由な表現や力強さもある楽器なんだということをたくさんの方に知ってほしいです。
小澤征爾やクラウディオ・アバドとの思い出にからめて述懐された、音楽への献身も忘れられない。インタビューの仕事は難儀だが、こうして新しい世界を開いてくれるからやめられないのだ。
2025年もどうか、いい出会いがありますように。
引用:吉野直子インタビュー「“エレガント”を超えて。自由で力強い『ハープの未来』」(リシェスNo.49 2024年9月28日 初出)
クラシック・プレイリスト、次回の担当分は12月10日より放送予定。テーマは「キャロル・オブ・ザ・ベル」です。毎朝5時台、JFN系列38の全国FM局とradikoタイムフリーでもお聴きいただけます。(※放送は終了しました。)
