2007年のキャッチは、The Princess Yearでキマリです。
絵本時代より「おひめさま」が大好きで、洋の東西を問わずプリンセス的なるものを探求し続け、プリンセス研究家を自称している私としては、それはひとつのライフワーク。
しかし、今年は別格なのです。
■MARIE ANTOINETTE
ソフィア・コッポラ監督作品『マリー・アントワネット』(1月20日ロードショー)。
以前カンヌでの酷評をお伝えした作品ですが、「ベルばら」が愛されつづけるわが国では、女性誌を中心に一大歓迎ムードでした。*1
ゆえあってか、薔薇のモティーフやフレーバーも流行中。
ただし、「セレブ気分」「究極のセレブ」という表面的なキャッチコピーに惑わされないでほしいのです。
ソフィアが描いたのは、アントワネットのあけっぴろげな感受性、美意識、孤独、葛藤、現実逃避……そういう人間くささ。
だからこそ『ヴァージンスーサイズ』のキルスティンに、ニュー・ロマンティックの音楽に、キャンディ・カラーが並んでいるのです。
だからこそ幕切れは、“ヴェルサイユ=青春の終わり”なのです。
もちろん、ソフィアが18世紀のフランス(=ロココ)が好きで、アントワネットとその周辺にスウィートな憧れを抱いていたことも事実。
なにしろ歴史上もっとも華やかで典雅、洗練と軽薄を極めたプリンセスです。
とっかえひっかえ現れるマカロン色のドレス*2、マノロ・ブラニクの靴、犬、清楚な花や庭園、そしてパリの老舗パティスリー「ラデュレ」のスウィーツ。
乙女なら、タイトルバックから失神寸前のはず!!
それはそれでよろしい!!
とあるインタビューで、ソフィアが真っ先に影響を受けたと語った映画は『アマデウス』。
さりげない色使いや陰影、劇場シーンなどにうなずけるところがあります。
サウンドトラックでは、バウ・ワウ・ワウのI WANT CANDYなど、ニュー・ロマンティックが大きく宣伝されていたけれど、これってもったいない!!
時代劇とポップ&ロックの融合は今に始まったことじゃないし。
実は映画全体には、ヴィヴァルディの協奏曲やクープランのクラヴサン曲がひっきりなしに登場します。
割合的には五分五分じゃないかな?
もちろん、ソフィアとブライアン・レイツェルの選曲は、いつもながら最高のセンス。*3
オペラは終盤、王妃が孤独を深めるときにかぶさるラモー《カストールとポリュックス》からの静謐なアリアが印象的で、これがまた、ウィリアム・クリスティの指揮なのです。若林恵さんをして、“太陽王ルイ14世のよう”と言わしめたマエストロも、きっと本望でしょうね!
先ごろ購入したDVD(もちろん限定版!!)の特典、未公開映像では、アントワネットゆかりのグルック《オルフェウスとエウリディーチェ》が撮影されていたこともわかりりました。
ここでエウリディーチェのアリアを歌うのは、スーザン・グラハム。
クラシックとロック、2つをつなぎ合わせる役目をしているのが、ダスティン・オハロランのピアノ。*4
雨の降りそぼるパリのスタジオにダスティンが赴き、一日中ピアノと向かいながら収録されたというロマンティックな作品が、ヴェルサイユに自然に溶け込んでいます。
■「ティアラ展」、「グレース・ケリー展」and more…
プリンセス気分を盛り上げてくれるのは、映画だけじゃなかった!
同20日からは「ティアラ展」@Bunkamuraザ・ミュージアム、4月にはモナコの王妃「グレース・ケリー展」@日本橋三越が開催されました。
クラシック・コンサートのチラシの絶望的なデザイン・センスと、展覧会CMの音楽センスは互角だと思う。
「目なら目、耳なら耳」しかない人ってそんなに多いのかな? もっと交流ができないのかな? というか、する必要があるはずです。
わたしは両方を大切にして、世界を変えたい。
アカデミー主演女優賞をさらった映画『クイーン』 に勇気づけられながら、プリンセス研究はつづきます。
*1 「ベルばら」はもはや、日本人の教養。映画のように無垢でスウィートなアントワネット像は日本人にはおなじみだが、実はニュアンスに大きな隔たりがある。
ツヴァイクの原作を読んだ池田理代子が、当初から重きを置いていたのは「革命」と「高貴な女王」。アントワネットは無垢なプリンセス→よき母、よき妻へ脱皮するようにすり変わってい。だからフェルゼンとも許されないプラトニック・ラヴを育み、革命のなかで悲劇に結ばれるまで、彼女から性のにおいはしない。フェルゼンも、思いを押し殺して(※萌えポイント)、戦場と革命を戦うことで男を上げる。
一方、ソフィアが描くアントワネットは、前述の「→」をこそ生きている。子どもでもない、大人でもない、モラトリアムな青春。自我のあいまいさと孤独に苛まれ野放図に過ごすヒロインは、最後にフェルゼンより、趣味やセンスは違うがリスペクトしあえる地味な「ぼく」=ルイを選ぶ。
母親(マリア・テレジア)との関係も暗示的。もしも萩尾望都がアントワネットを描いていたら、こういう話になったかもしれない。
※実際に萩尾先生は短編「あぶない壇ノ浦」において、源氏が身内殺しによって絶える歴史を父・義朝と兄弟との関係、トラウマという考察を巧みに用いて描き出しており、とても斬新だった。(『あぶない丘の家』小学館文庫所収)
*2 マカロンの色彩は、衣裳だけではなく映画全体を包み込む色彩になっている。
プロダクションデザイナーのK.K.バレットは語る。「ソフィアは、ある参考書を持ち出した。それは、ミント・グリーンやマゼンダ、カナリア・イエローなど、たくさんのマカロン・カラーで埋め尽くされていた。誰もが考えるロイヤル・ブルーやバーガンディーではなく」
これは、アントワネット本人がヴェルサイユの既成の伝統を次々破っていった史実(軽やかな素材のドレス、植物性の香水、入浴の習慣)とも共鳴している。「マリー・アントワネットが実際に住んでいたアパートメントのファブリックを見たとき、彼女の好きな色――ガーリーな色、春の色、ピンクとターコイズがとても新鮮だったので、その色を反映させようと思いました」とソフィア。「たくさんの衣裳はI WANT CANDYという曲の骨組みから出来ている。私とソフィアは、食べたいと思わせる色と素材の衣裳を選んだわ。最初は柔らかいけど、徐々にショッキングになるように」とは、衣装デザイナー(本作でアカデミー賞受賞)のミレーナ・カルネロの言葉。
そして、その“キャンディ&ケーキ”に具体的なイメージを与えたのが、ラデュレである。(アートデイズ刊のビジュアルブックより)
*3 ソフィアの映画がファッショナブルなのは、アカデミー賞を受賞した脚本、フォトグラファーの視点が生かされる映像とともに、音楽のセンスが極めていいことが要因だ。基本の選曲はソフィアが行い、そこから映像をイメージするという。彼女はミュージック・ビデオは手がけていないが、兄ローマンや元夫のスパイク・ジョーンズの影響から、自然とこの形になったのかもしれない。
ブライアン・レイツェルは、レッド・クロスやエールのドラマーで、ソフィア作品に欠かせない音楽プロデューサー兼作編曲兼スーパーバイザー。
ブライアン曰く「彼女は“わかっている”」。
音楽でもうひとつ注目すべきなのは、現在のソフィアの恋人トマ・マルス率いるヴェルサイユ出身のバンド、フェニックスが、劇中に出演して演奏していること。
もちろん衣裳&カツラ付き。
アントワネットの内面を反映する、いいシーンに仕上がっている。
こんなニュースも。
http://doops.jp/2007/02/air_1.html
*4 ダスティン・オハロランは、LA生まれで現在イタリア在住。90年代半ば、サラ・ラヴとともにデヴィックスを結成し、4枚のアルバムを出している。
本作起用のきっかけとなったアルバム『Piano Solo』(ベラ・ユニオン)は、LAのDJの目に留まり、「ロック・ラジオ局でクラシック」という話題になった。

![マリー・アントワネット (初回生産限定版) [DVD] マリー・アントワネット (初回生産限定版) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51QcEj5D6tL._SL160_.jpg)

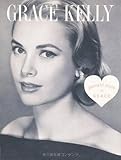
![クィーン〈スペシャルエディション〉 [DVD] クィーン〈スペシャルエディション〉 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51J4N9JdB3L._SL160_.jpg)